こんにちは。ろぼです。
ブログを始めたけれど、わかりやすい文章が書けない…。
どうせやるなら、楽しくやりたいですよね。
これからご紹介する3つのポイントを知れば、記事を書くのが楽しくなります。
- 書く技術は職人技だと思っている
- 文章の書き方って何が重要なの?
- 楽しくブログを継続したい
自己紹介
 ろぼ
ろぼろぼです。
WEBライター検定3級に合格しました。
ブログ歴8ヶ月目。
WEBライター検定3級の合格率は5%以下
WEBライター検定3級とは、クラウドワークス公式のスキル検定。
コンテンツマーケティングのプロ集団である「株式会社グリーゼ」監修のライティングテストです。
講義動画も検定も無料ですよ。
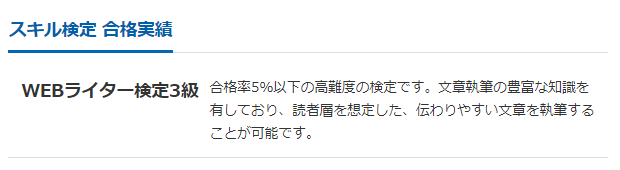
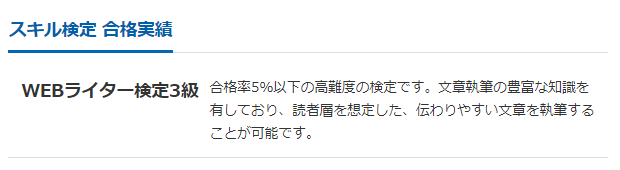


読み手にどうなってもらいたい?
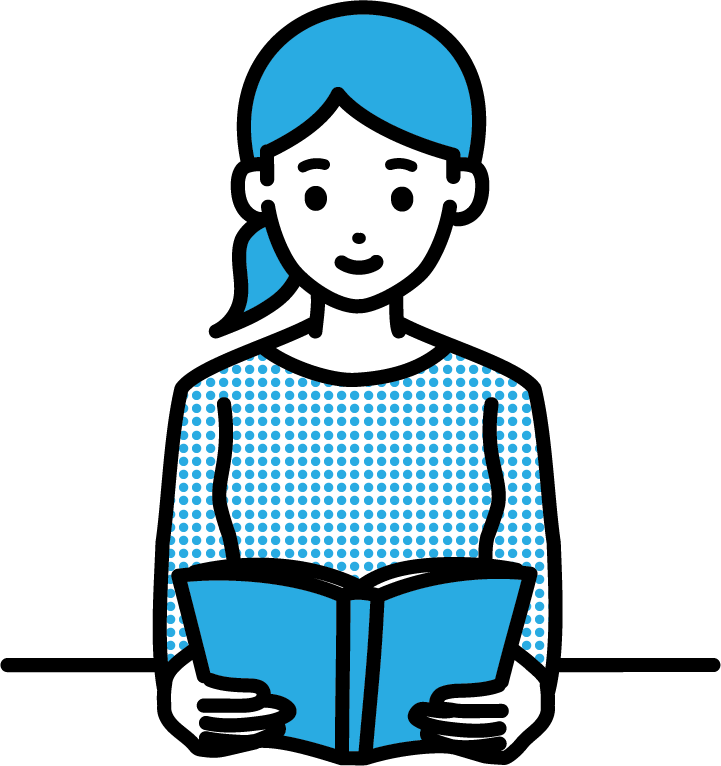
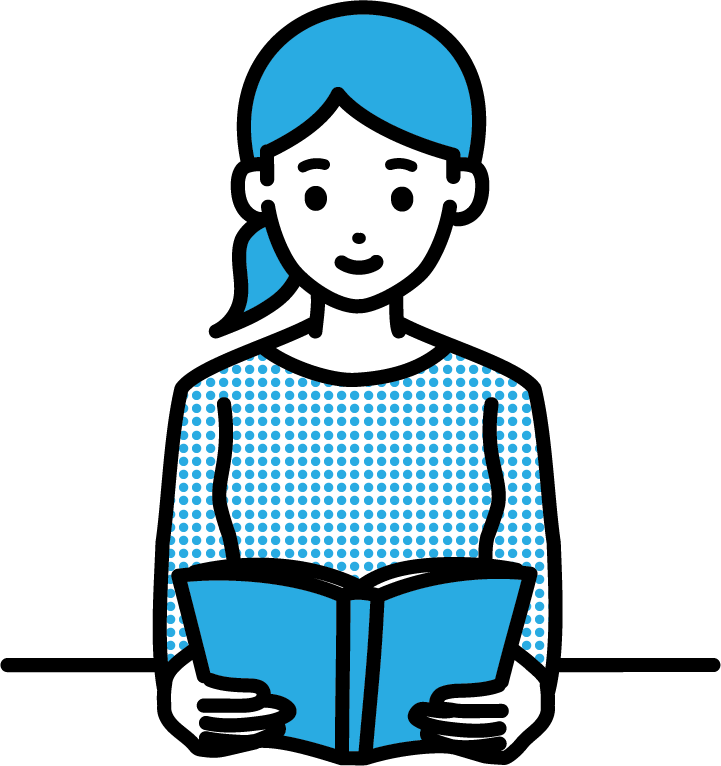
わかりやすい文章を書く以前に、記事を書く上で大切なこと。
それは「読み手(読者)にどうなってもらいたいのかを考える」です。
具体的には「誰に」「何を」伝えたいのかを考えましょう。
シンプルですが、ブログを始めて間もないときには、なかなか気づきませんでした…。
私のしくじり記事タイトル
- 〇〇で買えるオススメ商品3選
- 〇〇するためのテクニック
- 〇〇のやり方
書きたいテーマを探すのに精一杯だったので、「誰に」という部分が欠けていました。
しっかりわかってもらう説明を身につけている人というのは、あらかじめ相手のリサーチを徹底的に行っているのです。
相手に関する事前情報をできるかぎりかき集めます。
(中略)
相手が「どの程度知識をもっているのか?」「どんな考え方をしているのか?」
こういった知識や理解度のレベル、さらにはマインドまで知ろうとすることが大切なのです。
大塚 壮志 著 『東大院生が開発!頭のいい説明は型で決まる』より
読み手にどうなってもらいたいか考えるヒント
- 読み手の知識は?
- どんな考え方をしている?
- どの程度理解している?
「伝える」と「伝わる」の違い


なぜ、読み手のことを考える必要があるのでしょうか。
それは、読み手に行動して欲しいからです。
具体的には、新しい知識を得て試してみたり、商品やサービスを購入して生活が豊かになったりすること。
ここで1つ質問です。
「伝える」と「伝わる」の違いってご存知ですか?
主体は自分。
相手の理解や承諾、反応を受け取ることは前提とされていません。
主体は相手。
自分の投げかけから相手の行動や理解を促すもの。
文章を書くときには、「伝わる」ことを意識しましょう。
あえて初心者の立ち位置に戻る
何かを説明したいと思ったときは、あなたが知識やスキルを身につけてきたプロセス(過程)を思い出してみましょう。
わかりやすい文章を書くための3つのポイント
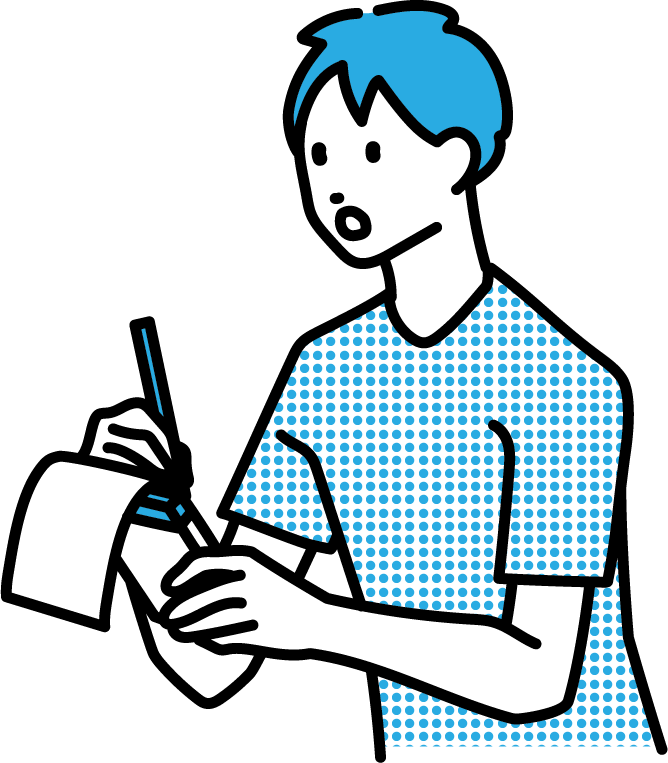
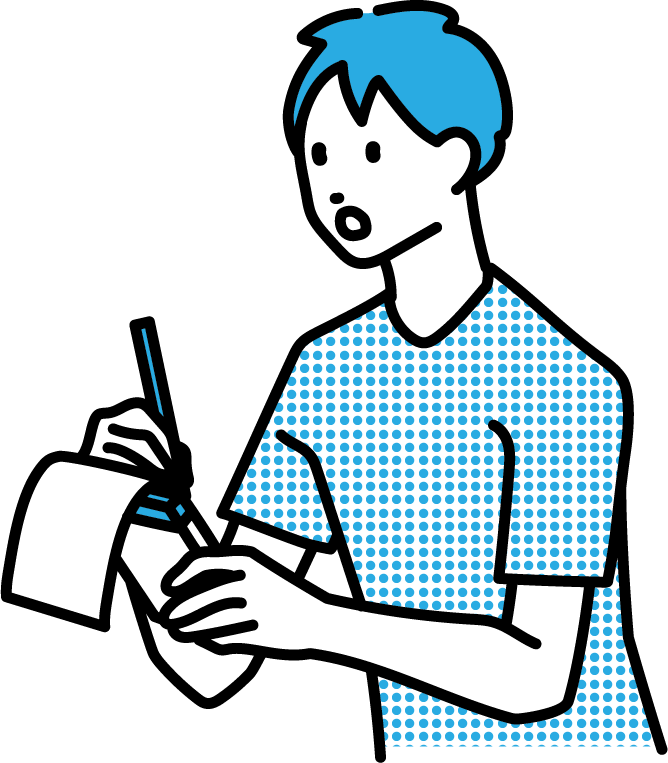
わかりやすい文章を書くための3つのポイントをご紹介します。
- 文章はシンプルに
- 伝わる文章には「型」がある
- 文章も見た目が大事
①文章はシンプルに
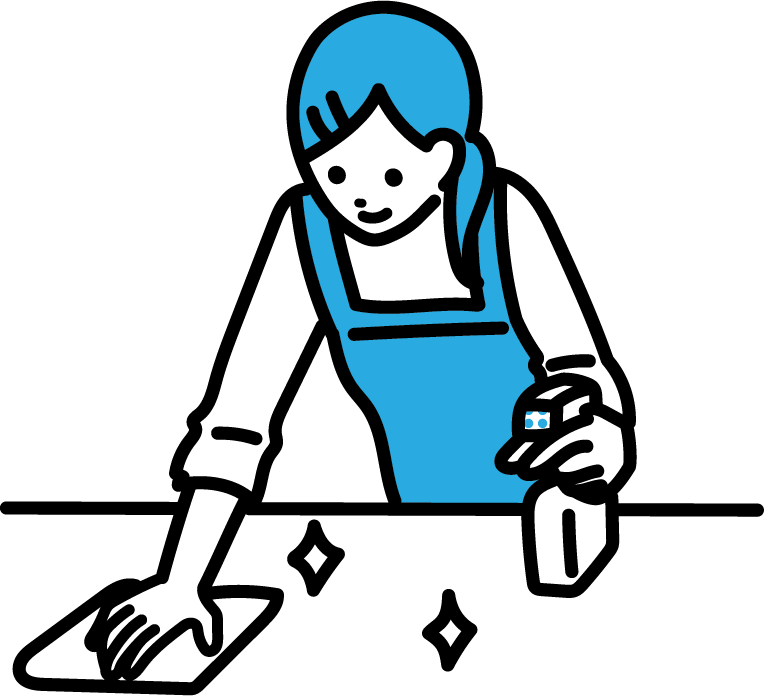
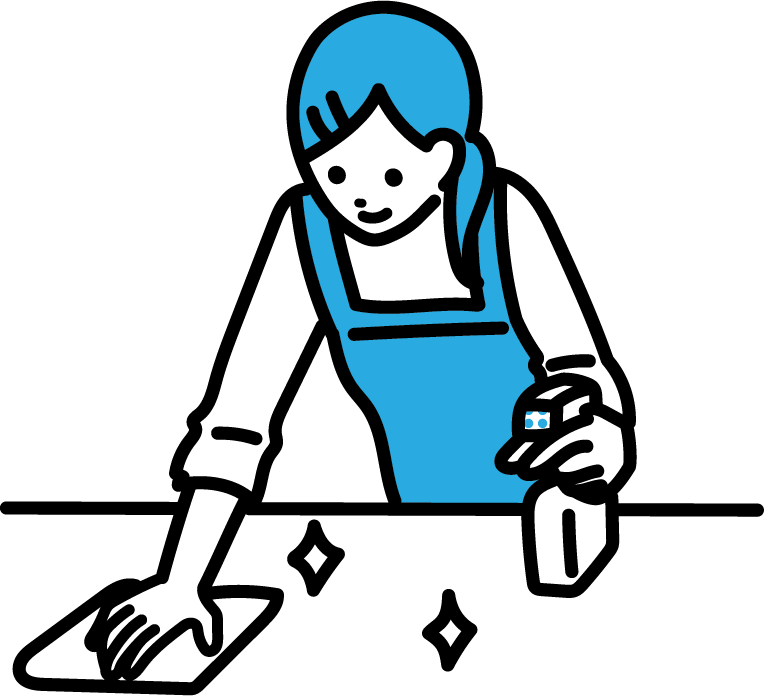
シンプルとは、不要な言葉を取り除く・簡潔に書く・1文を短くするとも表現できます。
(1)余計な言葉はとにかく削る
シンプルに書くことで、「内容が伝わりやすくなる」「リズムが良くなる」というメリットがあります。
削っても文章の意味が変わらない言葉は、どんどん削っていきましょう。
削りやすい言葉 5選
- 「そして」「しかし」「だから」などの接続詞
- 「私は」「彼が」などの主語
- 「その」「それは」「これは」などの指示語
- 「高い」「美しい」「嬉しい」などの形容詞
- 「とても」「非常に」「かなり」などの副詞
その他、意外とやってしまうのが、意味が重複する言葉。
- まず最初に→最初に
- はっきり断言する→断言する
- 余分な贅肉→贅肉
(2)1文の長さの目安は60文字以内
1文が短ければ、文章もおのずとシンプルになります。
長い文と短い文のメリット・デメリットを知って、場面ごとに使い分けましょう。
(3)一文一義
一文一義とは、「ひとつの文で、ひとつだけ伝える」ということ。
1文の中に複数の情報が盛り込まれていると、1文が短くても、わかりにくくなります。
- お客様の必要な情報を表示する機能を「マイページ」といい、快適にご利用いただくためには、プロフィールの設定が必要です。
- お客様の必要な情報を表示する機能を「マイページ」といいます。
快適にご利用いただくためには、プロフィールの設定が必要です。
②伝わる文章には型がある
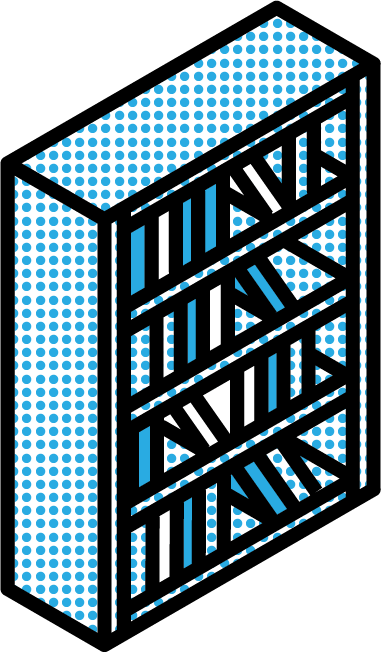
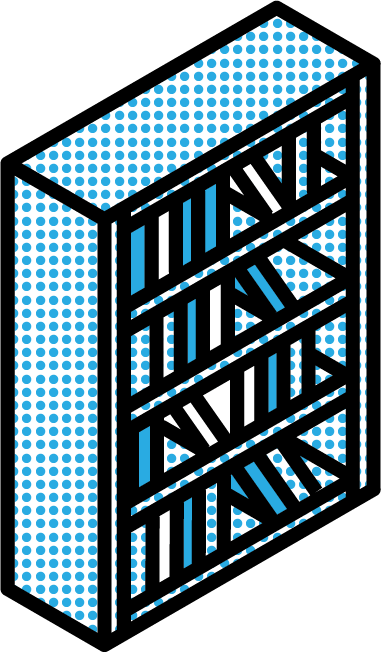
型とは、文章の流れを示すパターンのことです。
型に当てはめる6つのメリット
- 何から書けばいいか迷わない
- 書くスピードがアップする
- 文章の流れが良くなる
- 情報の過不足がなくなる
- 論理展開が破綻しにくい
- 言いたいことがはっきりする
(1)「結論が先、説明があと」の逆三角形型
結論を先に述べる型。
結論→説明→補足 と書き進めるほど重要度が低くなるため、「逆三角形」と呼ばれています。
(2)ブログは「PREP(プレップ)法」がおすすめ
結論を述べたあと、結論に至った理由と具体例を述べる型。
結論をはじめと終わりに2度書くことで、文章全体の説得力が生まれます。
P(Point)=ポイント、結論
あなたの主張や提案の「結論」を伝えます。
ここで伝える結論は必ず1つにしましょう。
R(Reason)=理由
結論の根拠となる「理由」を添えます。
E(Example)=事例・具体例
理由のイメージが湧く「具体例」を出します。
「具体例」の量を増やしすぎると、「結論」に収束させにくくなるので注意しましょう。
P(Point)=ポイント、結論、まとめ
再度「結論」を提示します。
(おまけ)論文は「序論→本論→結論」の三段型
論文やレポートは「結論があと」が原則。
論文に求められるのは、結論の正しさではなく、結論に行き着くまでの展開の正しさだからです。
③文章も見た目が大事
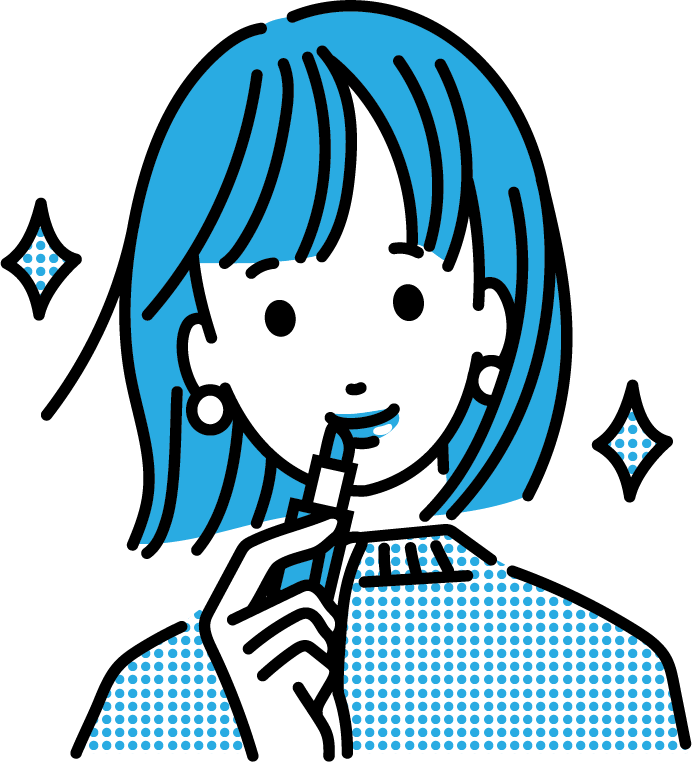
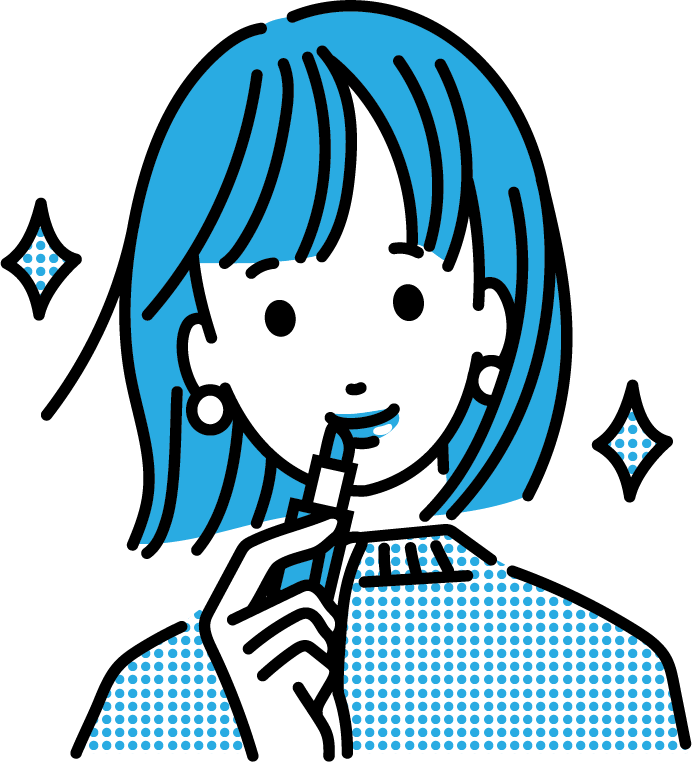
見た目が大事な理由。
それは、読みにくい文章は最後まで読んでもらえないからです。
あなたが途中で読むのをやめてしまうのは、どんなときでしょうか。
- 大量の文章がずらりと並んでいる
- 読めない漢字がたくさんある
- 文章のテンポ(リズム)が悪い
人は文章を読むとき、頭の中で音読しています。
よって、リズムが悪い文章は読みづらいと感じるのです。
どうすれば見た目が良くなるのか、3つのポイントをご紹介します。
(1)空白行を入れよう
空白行が無い例がこちら。
ビデオを使うと、伝えたい内容を明確に表現できます。[オンライン ビデオ] をクリックすると、追加したいビデオを、それに応じた埋め込みコードの形式で貼り付けできるようになります。キーワードを入力して、文書に最適なビデオをオンラインで検索することもできます。Word に用意されているヘッダー、フッター、表紙、テキスト ボックス デザインを組み合わせると、プロのようなできばえの文書を作成できます。たとえば、一致する表紙、ヘッダー、サイドバーを追加できます。[挿入] をクリックしてから、それぞれのギャラリーで目的の要素を選んでください。
圧迫感があり、読む気が失せますよね…。
内容の区切りで、空白行(改行)を入れてみましょう。
ビデオを使うと、伝えたい内容を明確に表現できます。
[オンライン ビデオ] をクリックすると、追加したいビデオを、それに応じた埋め込みコードの形式で貼り付けできるようになります。
キーワードを入力して、文書に最適なビデオをオンラインで検索することもできます。
Word に用意されているヘッダー、フッター、表紙、テキスト ボックス デザインを組み合わせると、プロのようなできばえの文書を作成できます。
たとえば、一致する表紙、ヘッダー、サイドバーを追加できます。[挿入] をクリックしてから、それぞれのギャラリーで目的の要素を選んでください。
同じ文章でも印象が変わりますね。
(2)漢字・ひらがなを書き分けよう
漢字とひらがな、それぞれのメリットとデメリットを確認しましょう。
- 漢字が多めだと「難しい印象で、内容が頭に入りにくい」
- 漢字が少ないと「やさしく、内容が頭に入りやすい」
(3)体言止めでリズムを生み出そう
体言止めとは?
文の最後を体言(名詞)で終わらせる表現方法。
体言止めを使った例文を見てみましょう。
セミナーでは、Aさんが効果的な文章術について解説しました。
体言止めを使うと…
- セミナーでは、Aさんが効果的な文章術について解説。
- セミナーで、効果的な文章術について解説したAさん。
- Aさんが効果的な文章術について解説したセミナー。
体言止めの、メリットとデメリットも知っておきましょう。
多用しすぎは良くないので、ほどほどにしましょう(;’∀’)
まとめ
わかりやすい文章を書くテクニックも大事ですが、記事を書く上で大切なこと。
それは「読み手(読者)にどうなってもらいたいのかを考える」です。
「誰に」「何を」伝えたいのかを考えて、伝わる文章が書けるようにがんばりましょう( ´∀` )
書くのが楽しくなる3つのポイントをおさらいします。
- 文章はシンプルに
- 伝わる文章には「型」がある
- 文章も見た目が大事
もっと詳しく知りたいあなたへ
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
もっと詳しく知りたいあなたへ。
オススメの書籍をご紹介します。
ぜひご覧ください。
無料でスキルアップしたいあなたへ
「WEBライター検定3級を受けてみたい!」「書くスキルをアップしたい!」あなたへ。
ぜひ、クラウドワークスに登録しましょう。
動画講義はいつでも・どこでも視聴可能。
「検定試験は受ける気がしない…」あなたも、動画講義を見るだけでスキルアップ間違いなしです。
登録費や年会費もかかりません。
無料です。
ぜひ、こちらから登録してみましょう!

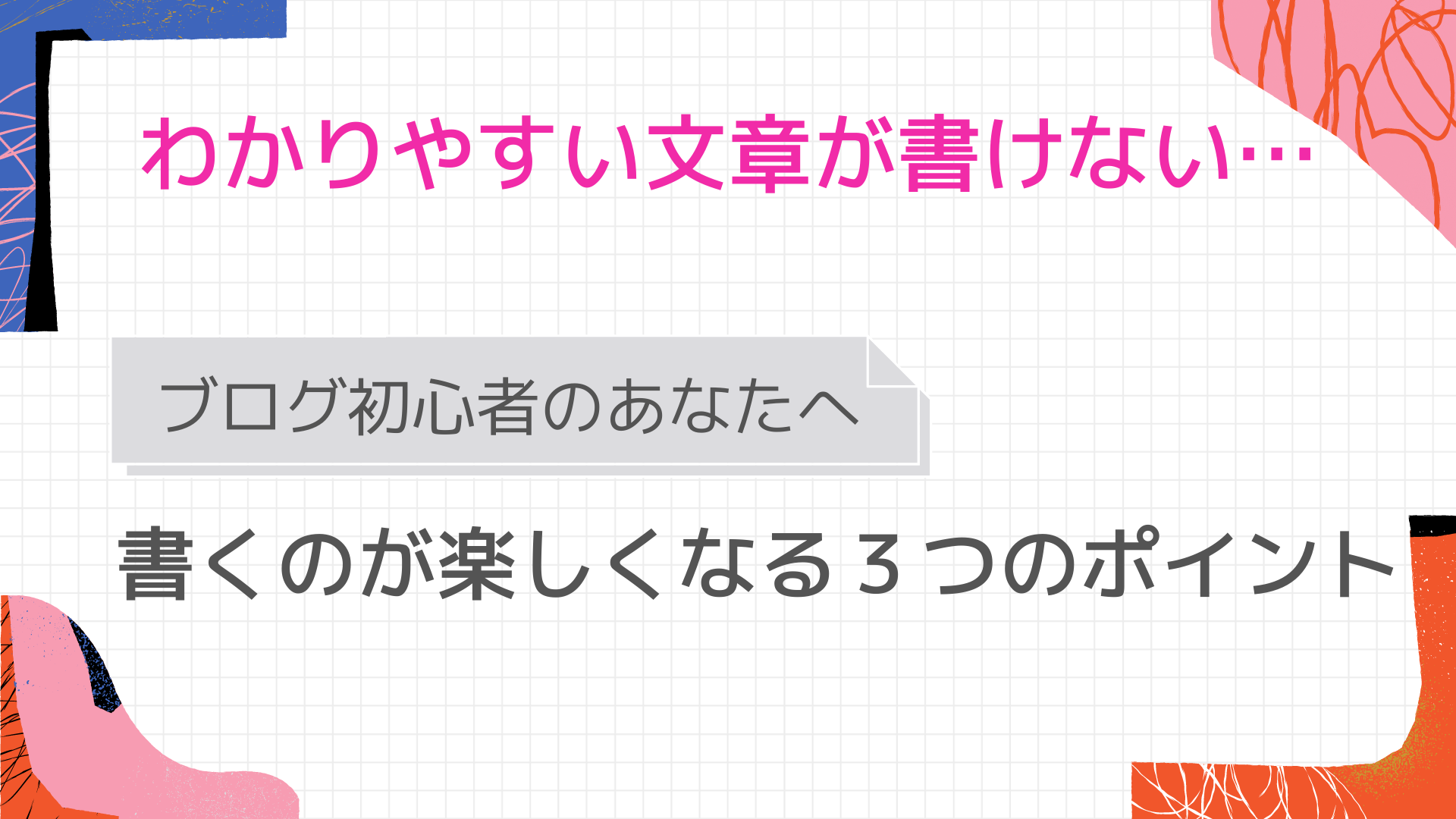



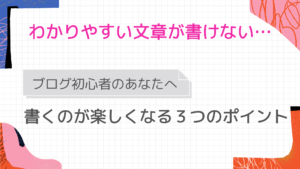
コメント