こんにちは。ろぼです。
普段から一生懸命学習しているのに、なぜか周りから評価されない…そんな悩みはありませんか。
もしかしたら、とある病にかかっている可能性があります。
今回は、優秀なのに評価されない人がかかる病とは?-越境学習のすすめ-を紹介します。
- 普段から学んでいるのに評価されない
- 自分が興味のある分野を積極的に学んでいる
- 自分の考え方はいつも正しいと思っている
今回ご紹介する内容は、オンラインスクールSchooにて「アンラーニング論 -変革をリードする人の働き方- (長岡 健 先生)」の講座内容をもとに、自分が調べたこと・感じたことをまとめました。
自己紹介
 ろぼ
ろぼろぼです。
適応障害で休職経験あり。
性格はHSP気質。
越境学習しましょう
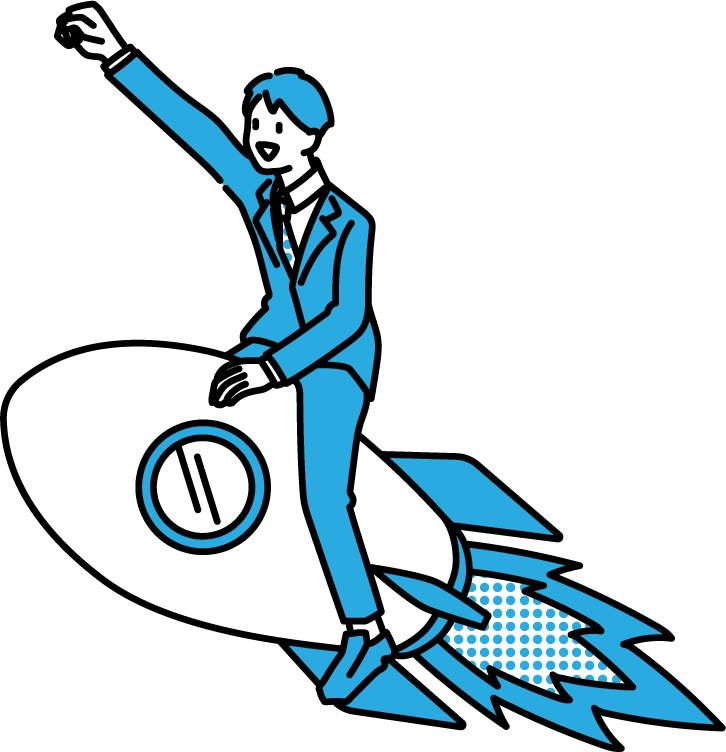
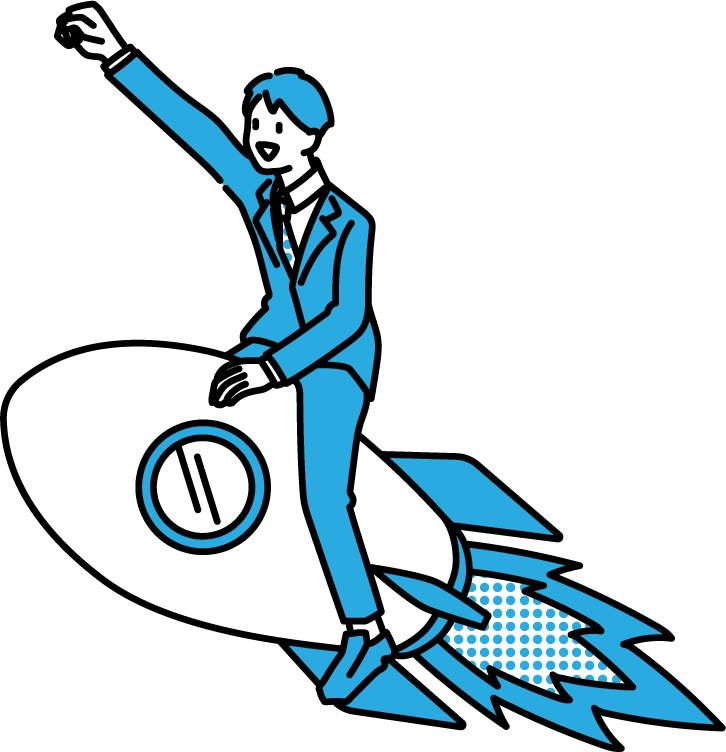
冒頭の「一生懸命学習しているのに、なぜか周りから評価されない 」と感じる理由の1つは、評価される価値基準が変わっていることに気づいていない、もしくは適応できていないからです。
もちろん、自分が置かれている環境に左右されることもあるので答えは1つではありません。
その他に考えられる理由
- 学んだことが身に付いていない
- 目に見える形で実践できていない
- 特定の上司との価値観が合わない など
この問題を解決するためには、越境学習することをオススメします。
越境学習とは
未来像を描く力を養うためには、普段興味がなかった分野の本を読んだり、異業種の人の話を聞いたり刺激を受けることによって、今までの当たり前な考え方を変える必要があります。
今までの習慣を棄てて、新しく学び直すことをアンラーニングといいます。
アンラーニングとは
ビジネスの場でよく使われる、ゆでガエル症候群の話を紹介します。
ゆでガエル症候群とは、経営や組織を語るときに使われるたとえ話。
現状にある程度満足してしまった人は、変化を求めて、さらに上を目指そうという気持ちが薄れてしまう場合があります。まさに“ぬるま湯に浸かった”状態。外部の変化を意識することも減っていき、気づけば自分だけ取り残されて取り返しのつかない状態になっているのです。
この話を聞いて「このままではダメだ」と危機感を持つ人は、越境学習を始めましょう。
「今のままでOK」と感じる人は、周りの変化を自分ごととして捉えるように意識を変える必要があります。
越境学習は意識すべきプロセス(過程)であり、アンラーニングは結果にすぎない。
優秀な人がかかる病「問題解決症候群」


なぜ越境学習が必要なのでしょうか。それは、自分は正しいという凝り固まった考え方を変えるためです。
問題解決症候群とは
優秀な人だからこそ陥りやすい病のことを、問題解決症候群と言います。
特 徴
- 「問題は与えられる」という前提から逃れられない
- 「問題には必ず唯一の正解がある」と思い込んでいる
- 「正解は誰かが教えてくれるはず」と想定している
このような特徴を持つ人はトラブルシューター型で、優等生タイプの人がなりやすいと言われています。一見すると、課題に対してまっすぐ取り組んで成果を出すので、悪い印象を持たない人もいるでしょう。
日本のビジネスパーソンはトラブルシューター型が多く、前例のルールに固執して、新しい考え方やモノの見方をすることが苦手な人が多いとも言えます。
トラブルシューター型とは逆の性質を持った人は長期ビジョン型。
それぞれの特徴を比較してみましょう。
トラブルシューター型の人は、長期ビジョン型になる素質がないのか?と感じますが、実は違います。
長期ビジョン型になれないのではなく、なろうとしないのです。トラブルシューター型はいわゆる優等生タイプの人が多く、不確実な答えのない問題に対しては、コスパが悪いと判断してエネルギーを使おうとしないのです。
越境学習を始めよう
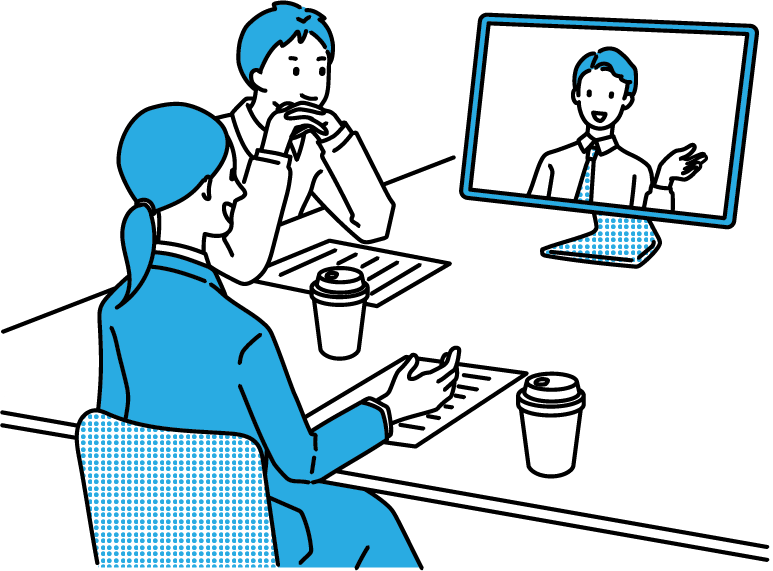
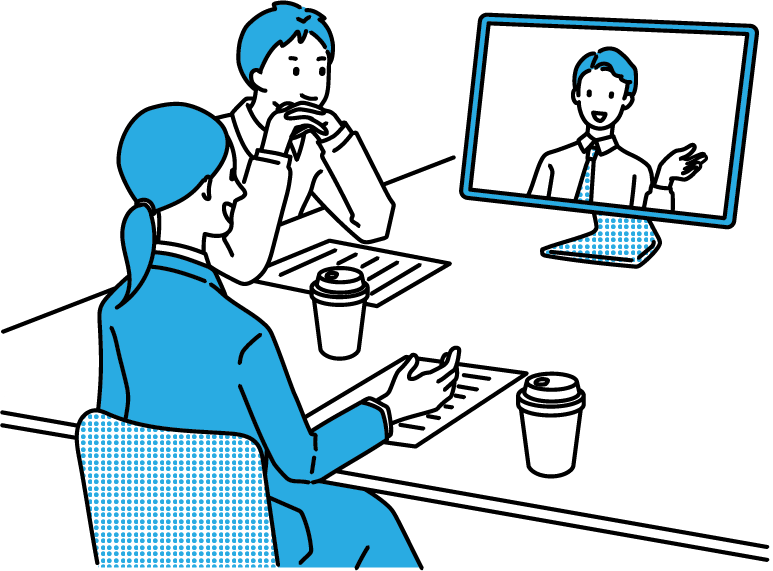
興味のないテーマ、直接的な利害関係が薄い人物、自分とは異なる価値観にあえて触れていくことが越境学習と紹介しましたが、具体的に何から始めればいいのでしょうか。
(社内)企業する、副(複)業する、ボランティアに参加するなど方法はたくさんありますが、まずはできそうなところから小さく始めていきましょう。
普段読まないジャンルの本を読む
普段ビジネス本しか読まない人は、歴史小説を読んだり、エッセイを読んだりしましょう。本を探すときは、リアルな書店に行くことをオススメします。
書店に行ったら、いつもは見ない棚をゆっくり歩きながら本を眺めると、不思議と読んでみたいと思える本が見つかります。
読書が苦手な方は…
読書が苦手な人も多いと思います。そんなときは「本を聴く」ことから始めてみませんか。通勤や家事の合間で気軽に始めることができるのでオススメです。
オンライン授業サービスを活用する
この記事を書くきっかけにもなった、Schoo(スクー)がオススメ。毎日情報が更新されるので、飽きずに学習できます。
スクーとは?
スクーは365日、無料のオンライン生放送授業を開催。「未来に向けて今あなたが学んでおくべきこと」をテーマに、働き方・お金・健康・テクノロジー・ビジネス・ITスキルなど、第一線で活躍している方の講座を受講できます。
勉強会や読書会に参加してみる
気心の知れた仲間だけではく、自分とは異なる考え方をする人たちと交流する場を設けましょう。
今はオンラインでの勉強会や読書会など数多く開催されているので、試しに参加してみるのもいいでしょう。
自分と似たような経験をしてきている人たち、自分と同じような考え方を持つ人たちのみと交流し、一緒に働くことは、仕事を進める上で一見、理にかなっていると思うかもしれません。しかし、結局それは「エコーチェンバー現象」に陥ることになります。つまり、閉じたコミュニティの内部にいて、自分と似たような意見を持った人々の間でコミュニケーションが行われても、結局は同じ意見がどこまでも反復され続けるだけです。
それとは反対に、自分とはまったく異なる文化、異なる世代、異なる場所にいる人の話を聞き続けることで、自ずと「世界共通の普遍的な真実、普遍的な意見というものがある」ことを発見するでしょう。すると、この地球や世界のどの場所にいてもコミュニケーションをすることが可能ということがわかります。
オードリー・タン著 「オードリー・タン デジタルとAIの未来を語る」より
【体験談】私は典型的なトラブルシューター型
自分で言うのもなんですが、まさに私はトラブルシューター型。
言われたことや与えられた業務の範囲内では、確実に成果を出そうとしますが、先を見越した不確実な問題を想像することが苦手。
仕事の効率を上げるためにPCスキルを学ぶことが好きだったり、人との付き合い方に興味があって、対人関係に関する書籍を読むことが好きだったりします。
そのため、学習する分野がPCスキル・対人関係のノウハウに偏っていました。
今起きている問題の対処はそれなりにできるのですが、まだ起きていない問題に対して長期的に深く考えることは避けてきました。
今まで成功してきた体験をもとに、自分が得意な型に当てはめて仕事をしていたため、異動して環境がガラッと変わったタイミングで、適応障害・抑うつ状態を発症。
適応障害を発症した原因は、劣悪な労働環境だったこともありますが、アンラーニングという学習方法を取り入れていたら、状況が変わっていたかもしれないな…と今は思います。(会社を辞めたこと自体は全く後悔していませんが…)
まとめ
今回は、 優秀なのに評価されない人がかかる病とは?-越境学習のすすめ-を紹介しました。
越境学習は意識すべきプロセス(過程)であり、アンラーニングは結果にすぎない。
考え方が凝り固まらないように、まずは普段興味がなかった分野の本を読んだり、異業種の人の話を聞いたり刺激を受けてみることから始めてみませんか。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
書籍の紹介
2021/12/20発売予定
好評発売中
読書が苦手な方は…
読書が苦手な人も多いと思います。そんなときは「本を聴く」ことから始めてみませんか。通勤や家事の合間で気軽に始めることができるのでオススメです。

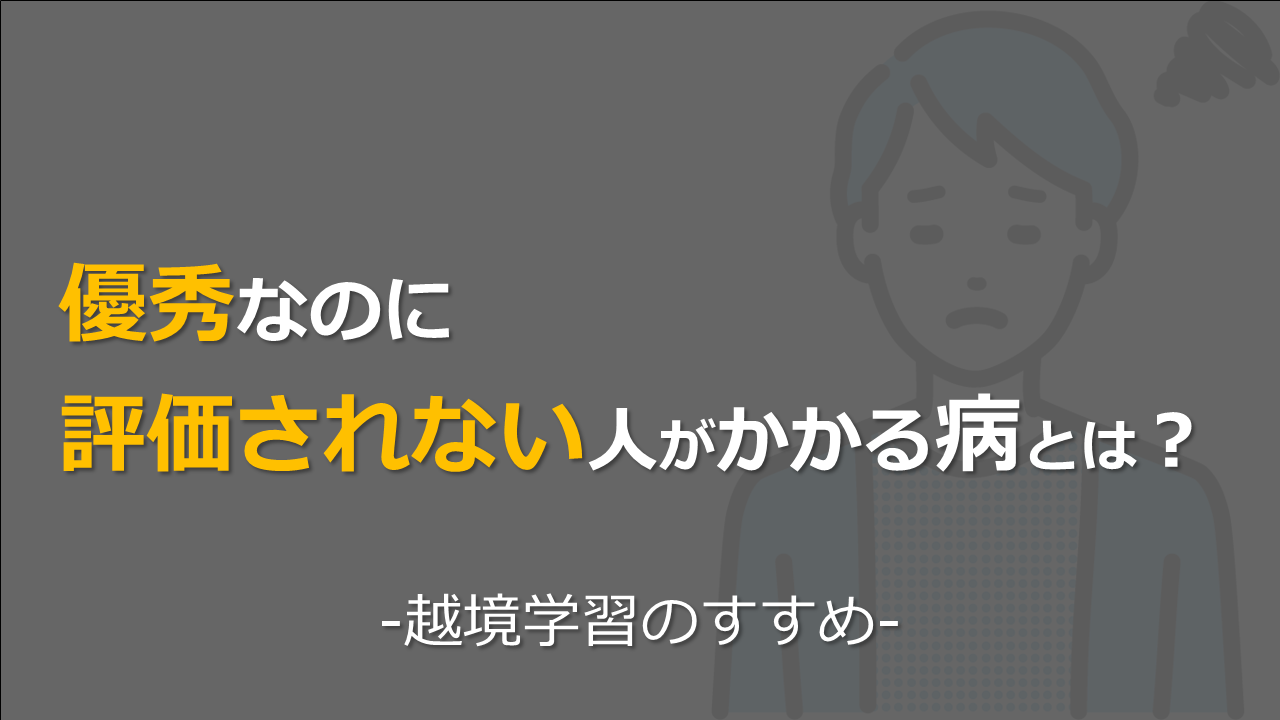


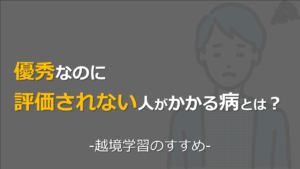
コメント